- 1 はじめに:なぜ今、個人メディアの未来について語るのか
- 2 AI Overviewの時代が到来:情報は“答え”に変わった
- 3 AI訴訟とライセンス問題:情報の“無断利用”はどこまで許されるのか?
- 4 AI企業が突き進む“グレーゾーン”と、発信者が直面するジレンマ
- 5 AIが奪ったのは「情報の価値」、残るのは「体験の価値」
- 6 個人メディアの希望:むしろ今こそ「個」が強い
- 7 収益低下時代に備えて:分散と長期視点がカギ
- 8 今、発信者にできること:AIと共創するメディア戦略
- 9 これから残る「発信者」とは誰か?
- 10 終わりに:AI時代の発信で生き残るために必要なこと
- 11 【最後に】情報発信と安全の両立。ノマド時代のVPNは“保険”である
- 12 もっとリアルな交流や質問は、Facebookグループでどうぞ!
はじめに:なぜ今、個人メディアの未来について語るのか
ここ数年、僕は英語コーチング事業を軸に、自社メディアで2,700本以上のブログ記事を運営してきました。SEOの上位表示も多く、経験ベースの良質な記事を作り続けてきたという自負があります。
でも、2024年から空気が変わりました。
AI OverviewやAI Modeの登場で、ユーザーが「記事を読まなくても答えが手に入る時代」が一気にやってきたのです。検索結果の構造が変わり、情報が“表示されるもの”から“要約されるもの”に変化した感覚。
「正直、これから個人ブログにどんな価値があるのか?」
僕自身が強くそう感じ始めたのが、この数ヶ月のリアルです。
AI Overviewの時代が到来:情報は“答え”に変わった
Webアクセスが減少しているという体感
事実として、検索パフォーマンスはむしろ向上しています。
たとえば:
- 平均掲載順位:過去最高の7位台
- 上位記事はCTR(クリック率)4〜5%超え
にも関わらず――
全体の平均CTRはわずか0.7%まで下落。
つまり、「検索には出ているけど、クリックされない」状態が起きている。これはまさに、AIが答えを表示してくれているから、記事が読まれないという構造です。
ブログが“集客装置”から“趣味メディア”に変わる危機
本来なら集客の柱であるはずの自社メディアが、いまや「読まれない存在」に変わりつつある。
このままでは、ブログ運営のROI(投資対効果)がどんどん悪化し、やがて趣味化していく可能性さえある。実際に、更新を止めるブロガーやメディア運営者が急増しているのも事実です。
「認知されない時代」に、発信者はどう向き合うべきか?
AIが最初に“要約”し、“答え”を表示する時代では、「その人の記事を見に行く」より、「AIが拾ってくれるか」が勝負になる。つまり、SEOというより「AIO(AI Optimization)」の時代。
とはいえ、ここにこそ大きな落とし穴があります。
AIに拾われない=存在しないに等しい。
でも、AIに拾われるだけ=他と差別化されない。
これは、ただ情報を「早く・わかりやすく」出すだけの戦いでは勝ち目がないことを意味します。
AI訴訟とライセンス問題:情報の“無断利用”はどこまで許されるのか?
すでに始まっている、AI企業への訴訟の動き
AI企業によるコンテンツの無断利用を巡って、世界各国で訴訟が次々と起こっています。
主な訴訟事例(2023年〜2024年)
- New York Times vs. OpenAI & Microsoft
➤ NYTの記事が事前許可なくGPTに学習されていたとして、著作権侵害で訴訟(数十億ドル規模)。
➤ OpenAI側は「Fair Use(公正利用)」を主張するも、法的決着は未定。 - Getty Images vs. Stability AI(英国・米国)
➤ 写真素材を無断で学習データに使ったとして、画像生成AIの法的リスクが浮き彫りに。 - 作家団体(The Authors Guild)やノンフィクション作家らによる集団訴訟
➤ 書籍やエッセイが、AIの学習に使われたことを問題視。
これらの訴訟は、AIがどこまで“引用”や“学習”してよいのかというボーダーラインを揺さぶっており、今後の判例によっては、AI企業のビジネスモデル自体が揺らぐ可能性もあります。
なぜ今「AIライセンス構想(Revenue Share)」が浮上しているのか?
こうした訴訟を背景に、AI企業と発信者(コンテンツ制作者)の間での「収益分配モデル」の必要性が叫ばれるようになっています。
例:AIライセンスモデルの構想とは?
- AIが引用・要約するたびに、発信元に「微小な使用料(マイクロペイメント)」が入る仕組み
- 記事・動画・画像・コードなど、あらゆるコンテンツに「AI用ライセンス情報(タグ)」を埋め込む
- GoogleやOpenAIなどが、これを読み取って分配計算を行う
しかし現時点では、構想だけが先行し、明確なルールも実装も未確定。
その間も、AIは発信者の情報を吸収・再構成し続けており、「やったもん勝ち」の様相を呈しています。
だからこそ、グレーゾーンで発信者が選ぶべき2つの道
- ライセンス側に回る(大手メディア・専門メディア)
➤ AIと契約し、使用を認めつつ対価を得るポジションに移行。 - 個人メディアとして戦略的に“拾われる”記事を作る(個人・中小)
➤ 独自体験や感情・視点・動画・声などAIに完全再現できない要素を混ぜる。
➤ 構造化データ・FAQ・動画・短尺要約・失敗談・CTAなどを駆使して、AI Overviewに引用されやすくする。
✅ AIが引用しても読者が「元記事を読みたくなる」ような、独自性のあるストーリー・構造・表現が必要。
AI企業が突き進む“グレーゾーン”と、発信者が直面するジレンマ
著作権を超えた「学習の自由」が、グレーゾーンに踏み込む
現時点で、OpenAIやGoogleなどのAI企業は、公開されたウェブ上の情報を自由に学習・要約・引用するスタンスを取っています。
表向きは「Fair Use(フェアユース)※米国基準」や「Webクローリングは合法」といったロジックで動いていますが、以下の点でグレーゾーンとされています:
- 著作権者の明確な許諾がない
- 一部は有料会員向けのコンテンツまで学習対象に含まれている
- 引用元が表示されないことも多い
- AIが情報を再構成することで“剽窃の境界線”があいまいになる
こうした中、海外ではすでに「AIによる情報の“盗用”ではないか?」という訴訟や議論が活発化しており、まさに“前例のない戦場”で線引きを試みている状態です。
彼らは「あとでルールを作る」スタンスで動いている
AI企業の特徴は、「まず作って出す → 問題が起きたら修正する」という、いわば「ルールより技術が先」型のアプローチ。
このスタイルは、テック業界の常套手段とも言えますが、同時にこうした大規模AIモデルがグレーゾーンを“突き進む”構造を作っているとも言えます。
- 著作権をめぐるルールは国ごとに異なり、曖昧なまま進行中
- 「非営利目的の学習は合法」などの法的抜け穴を利用
- 膨大な情報を一気に学習させて、事後的に整理すればよいという考え
つまり、AI側が一気に“食い尽くして”、後から「著作元への報酬」や「表示義務」を導入する流れであることは、冷静に認識しておく必要があります。
発信者は「黙認しながら、利用する」バランスが求められる
このような状況下で、発信者・ブロガー・個人メディアが取るべき立場はシンプルです。
「倫理的に許せなくても、活用しながら生き延びる道を探る」
- 自分の発信がAIに引用されたらラッキーと考える
- 「拾われる設計」に記事を最適化する
- 同時に、AIが真似できない部分(失敗談・裏話・感情の起伏)を記事に注入
- 最悪引用されたとしても、読者が「直接読みに来る価値」を埋め込む
グレーゾーンである以上、「怒って止める」よりも「流れを見切って武器に変える」方が、個人にとっての生存確率は高まります。
✅ AI時代の発信者に必要なのは、「正しさ」ではなく「戦略と適応力」
その中で、発信者がどう“表現力と設計力”で差をつけるかが問われる時代なのかもしれません。
AIが奪ったのは「情報の価値」、残るのは「体験の価値」
「情報の正確さ」はAIの得意領域になった
AIの登場で、情報の正確性やスピードは誰でも手に入れられるものになりました。
ChatGPTに聞けば、「雰囲気=atmosphereではない」みたいな話も一瞬で出てきます。
ここで問題になるのは、発信者の“意味付け”や“解釈”が消えてしまうことです。
たとえば、以前は「失敗談つきの表現解説」や「リアルな英語学習の悩み」に共感が集まりましたが、AIが答えを出してしまうと、「それ以上の時間をかけて読む意味ある?」と感じる人が増えてきます。
でも逆に言えば、“ただの情報”だけでは差別化できない時代がきたとも言えます。
AIが真似できないのは「物語」「痛み」「選択」
ここで重要なのは、「AIにできないことは何か?」を真剣に考えることです。
そしてその答えは、かなり明確です。
- 本当に悩んだ失敗談
- 自分しか体験していないプロセス
- 判断の葛藤や価値観の転換
- 感情がにじむ選択の記録
こういったものは、AIには真似できません。
これは、単なる体験談ではなく、「思考と感情のログ(記録)」としての価値があります。
つまり、AI時代に強い発信者とは、“感情×判断”を物語として編める人間です。
個人メディアの希望:むしろ今こそ「個」が強い
「自分の人生」をコンテンツ化できるのは個人だけ
AIが量産する一般的な記事では、「この人の話が聞きたい」とは思われにくい。
でも個人であれば、自分の失敗、悩み、背景、育ち、人生の選択を、“誰にも真似できない独自のストーリー”としてコンテンツに落とし込める。
「旅×英語学習×ノマド×子育て」
「フィリピン &オーストラリア ×留学×コーチング事業の立ち上げ」
「FIRE ×ChatGPTで戦略×仮想通貨投資」
こういう文脈は、大手では扱いにくい。
でも、個人なら一貫した“人間の物語”として届けられる。
ここにこそ、個人メディアの逆転チャンスがあります。
大手にはできない“混ざり合い”が、個人の武器になる
企業メディアは「一つのテーマに集中」する必要があります。
でも個人は、英語の話の中に投資の話を入れてもいいし、英語学習を哲学と結びつけてもいい。
つまり、異なる世界観を“混ぜる自由”がある。
これは、いまのAIでは難しい表現です。
なぜなら、AIはあくまで「多数派の平均」から生成するため、“混ざった個性”はノイズとして処理されやすいからです。
逆に言えば、個人でしか語れない“多層的なストーリー”を持っている人ほど、今後のAI時代では希少性を持てる。
これはまさに、「人間にしかできない知的編集」だと思います。
収益低下時代に備えて:分散と長期視点がカギ
アクセスが取れても、収益が減るリアル
検索上位に表示され、CTRもそこまで悪くない。
でも、集客や申込につながらない。
これは、今僕が直面しているリアルです。
英語コーチング事業では、過去最高の検索順位を取っていても、「申し込みの数」が戻ってこない。
Googleの検索結果の変化によって「必要な情報は概要だけでいい」という層が増え、問い合わせに至るまでの接触が極端に短くなっていることが原因だと思います。
つまり、「検索される」=「見込み客が増える」ではなくなってきている。
キャッシュフローとブランドを分けて考える時代へ
この流れの中で僕が意識しているのが、キャッシュフローの源泉を分けること。
- ✅ 英語事業のブログコンテンツ → 信頼とブランドの資産化
- ✅ 仮想通貨・長期投資 → キャッシュフローのセーフティネット
ブログコンテンツからの集客から“すぐに収益が上がらない”かもしれない。
でも、信頼や認知をじっくり蓄積しておけば、次の事業や提案に繋がる資産になる。
だからこそ、今のうちに別軸での収益源(投資、コミュニティ、アフィリエイトなど)を仕込みながら、「ブログ=長期ブランド育成」へと考え方をシフトしていく必要があります。
仮想通貨や長期投資で時間を“買う”という発想
現に、僕自身はこの3年間で仮想通貨の資産をコツコツ積み上げ、年末には1,000万円突破、そして2026年には、1200〜300万円ほどに到達することを見込んでいます。つまり年間僕が使うお金を通貨が勝手に稼いでくれているということです。
これによって、
- ブログで今すぐ集客できなくても焦らない
- 数ヶ月〜1年スパンで「AI最適化」を実験できる
- 資金面でメンタルが安定する
という“時間を買った余裕”が生まれます。
これは、発信の質を落とさず、冷静にAI時代を戦い抜くための土台になっています。
今、発信者にできること:AIと共創するメディア戦略
2700本のブログを、AI時代対応にリライト中
現在僕は、過去6年で書いてきた2,700本のブログ記事を1本ずつチェック・修正しています。
やっているのは、主に以下のような対応です:
- ✅ 冒頭に「即答+例文」を設置(AIに引用されやすくする)
- ✅ 自分の体験や失敗談を要点化して追加
- ✅ YouTube動画や音声を記事内に埋め込み
- ✅ 構造化データ・FAQ・JSON-LDマークアップの導入
- ✅ 関連記事との内部リンクを最適化
このように、「AIに拾われる前提で設計する」ことが、現代SEO(=AIO)においては重要になっています。
AI時代の正解は「拾われつつ、読ませる」
僕が最近強く実感しているのが、
「AIに拾われる=AIに代替される」ではない
ということ。
むしろ、AIに引用され、概要で見られた上で「もっと深く知りたい」と思わせる。
そのためには:
- AIには出せない“思考の過程”を残す
- ストーリーと感情で補足する
- 迷いや悩み、葛藤をコンテンツに変える
これが、“AIとの共存型コンテンツ”だと考えています。
これから残る「発信者」とは誰か?
AIと共存できる“人間らしさ”が武器になる
正直、AIに代替される情報発信は今後どんどん淘汰されていきます。
でも逆に、AIでは補えない「体験・物語・視点」を持つ人の発信は、より光る時代になるとも感じています。
- 失敗をさらけ出せる人
- 疑問や迷いを文章にできる人
- 自分の思想・価値観を発信にのせられる人
こうした“感情とコンテキストを持った発信”は、
AIの合理性だけでは辿り着けない領域です。
誰もが「自分のストーリー」で戦える時代
ここが重要なポイントですが、今の時代は「大手メディアのように大量のコンテンツを用意しなければ生き残れない」わけではありません。
むしろ、大手は個人の迷いや葛藤をコンテンツ化しにくいという弱点を抱えています。
だからこそ、個人の自由な視点・過去の体験・価値観の変化をドキュメンタリーのように描く発信が、ニッチな支持と深いファンを生むんです。
そして、それがまさに今の検索ユーザーが求めている「人間らしい納得感」に繋がっていく。
終わりに:AI時代の発信で生き残るために必要なこと
「拾われるために最適化」×「読まれるために人間らしく」
僕自身が感じているのは、
これからの時代はテクニカルなSEO対策だけでは不十分だということ。
- AIに引用されやすい構成に最適化する(即答+例文、構造化データなど)
- AIで代替されない体験やストーリーを注入する
- マルチメディアで伝える(動画・音声・チャートなど)
- 知識ではなく「解釈」や「文脈」を伝える
つまり、「AIに拾われるように設計する × 読者の心に届くように人間らしく書く」の両方が必要なんです。
検索に期待しすぎない。「見られる」以外の価値を育てよう
今の時代、検索結果に表示されたとしても、
「読まれる」→「信頼される」→「選ばれる」には距離がある。
だからこそ、
- コミュニティ
- プロダクト
- コース
- コンサル
- ブランド
など、発信の“その先”にある価値を、
小さくても着実に育てていく必要があります。
最後に
AIはもう止まらない流れです。
でも、人が人に伝える意味は、むしろこれからのほうが強くなると、僕は思っています。
「自分にしか書けない」
「自分だから伝えられる」
そんなものが、AI全盛の中でも必ず残っていく。
だからこそ、
いま情報発信が苦しいと感じている人も、
“数”より“深さ”で勝負できる武器を一緒に磨いていきましょう。
【最後に】情報発信と安全の両立。ノマド時代のVPNは“保険”である
ここまで「AI時代の個人メディアと生存戦略」についてお話してきましたが、もう一つ、現代のノマドにとって見落とせないのが『オンラインの安全』です。
特に以下のような活動をしている人にとって、VPNの利用はもはや“保険”に近い存在になっています。
✅ VPNが必要になる主なケース
- 日本の銀行・証券口座にアクセスしたいのに、海外IPだとブロックされる
- SNS(X、TikTok、Instagramなど)の表示や投稿が制限される国に滞在
- パブリックWi-Fi経由でクレカやパスワード情報が抜かれるリスクがある
💥 実際、私自身もタイ滞在中にクレジットカードを2度ハッキングされました。
幸い損失はなかったものの、再発行などに数週間かかり、日常生活や事業にも影響が…
➤ 安全×自由を守る「VPNの導入ガイド」まとめました
ノマド向けにわかりやすくまとめた記事があるので、まだVPNを使っていない方はこちらを参考にしてみてください👇
🔗 海外ノマド生活でVPNが必要な理由とおすすめ対策(実体験ベース)
もっとリアルな交流や質問は、Facebookグループでどうぞ!
ブログや記事で得られる情報も良いですが、やはりリアルな人との交流から得られる気づきや安心感は別物です。
✅ 「AI時代の発信どうしてる?」
✅ 「VPNどれ使ってる?」
✅ 「実際に〇〇国で使える銀行アプリある?」
など、気軽に聞ける仲間がほしい方は、ぜひ私が運営するFacebookグループへご参加ください。
👉 🌏 リモートノマド&英語ライフ実践コミュニティ(Facebookグループ)
あなたの発信も、働き方も、生き方も、もっと自由に。もっと戦略的に。
共に次の時代を、切り開いていきましょう!
The Remote Digital Hubをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。










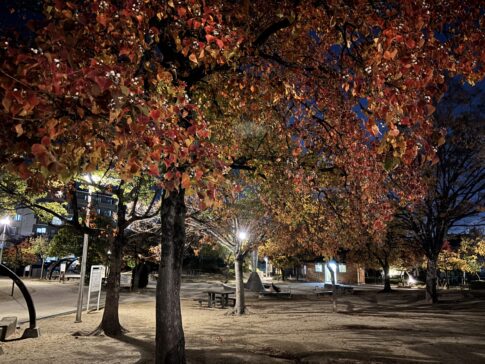


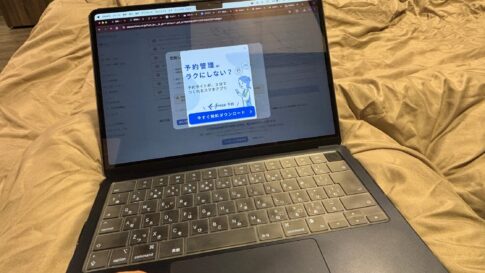



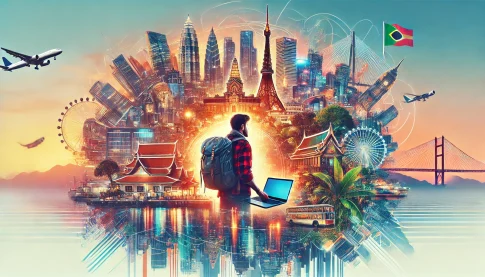







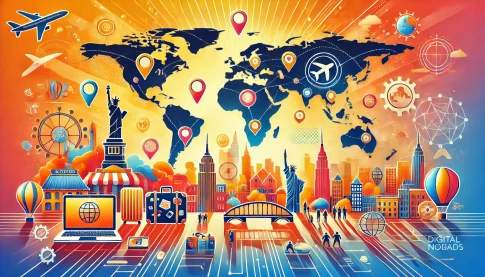


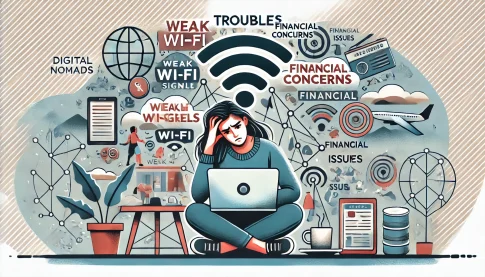
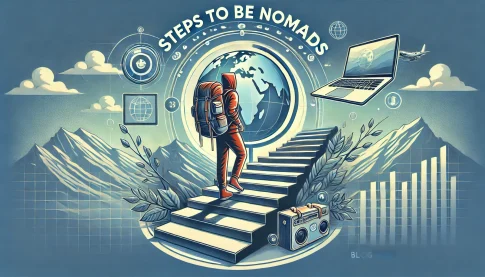

コメントを残す